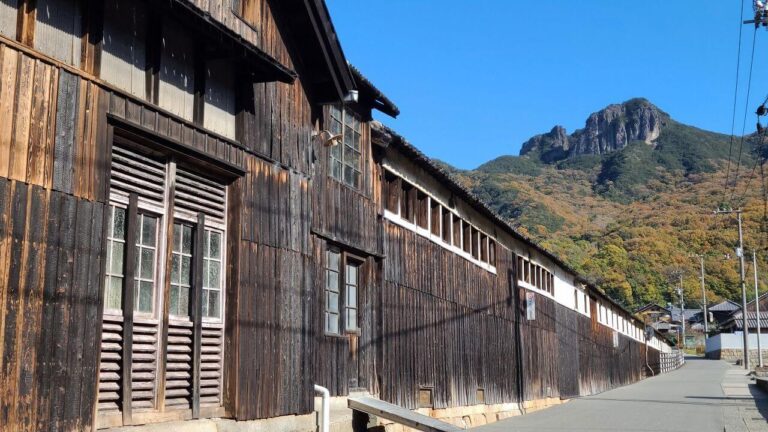高血圧や生活習慣病の予防のため、減塩はとても重要です。特に腎臓病など、塩分やカリウム制限が必要な方にとって毎日の食事づくりは大きな課題です。そうした中で「減塩とおいしさの両立が難しい」「塩分とカリウム制限のために使える調味料がわからない」という声をよく耳にします。
実は、適切な減塩調味料選びと使い方の工夫でこれらの悩みは大きく改善できることをご存知ですか?
しかしながら、スーパーに数多く並ぶ減塩調味料に「何を選んだらいいかわからない」と悩んだり、買ってみたけど「味が決まらない」「なんとなくおいしくない」と、多くの方が減塩調味料を上手く使いこなせていないのが現状です。
そこで今回は、制限食宅配サービスを展開するウェルネスダイニング株式会社の管理栄養士による専門的な監修のもと、減塩調味料とカリウム制限調味料の選び方や効果的な使い方、おすすめの商品について詳しくご紹介します。「おいしさ」も「減塩」もどちらも楽しく続けられる、あなたにぴったりの調味料を見つけてくださいね。
減塩・カリウム制限が必要な理由とは?

塩分を摂りすぎると、血圧が上昇して高血圧となり、心疾患など大きな病気のリスクが高まります。血圧の上昇を防ぐために減塩が効果的です。
厚生労働省がまとめた「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、1日の食塩摂取量の目安が以下のように定められています。
| 1日あたりの食塩摂取量の目安 |
| 成人男性 | 7.5g未満 |
| 成人女性 | 6.5g未満 |
| 高血圧及び慢性腎臓病の重症化予防(男女とも) | 6.0g未満 |
腎臓病の場合、カリウムを排出しきれず体内に溜まったカリウムが不静脈や心停止などを引き起こす恐れがあるため、塩分制限だけでなくカリウム制限が必要となります。
腎臓病の場合の最適なカリウム摂取量は、腎機能の重症度合によって異なります。日本腎臓学会が定める「慢性腎臓病に対する食事療法基準 2014 年版一部改変」に以下のように記載されています。
| 1日あたりのカリウム摂取量の目安 |
| ステージ1~ステージ3a | 制限なし |
| ステージ3b | 1日あたり2000mg以下 |
| ステージ4 | 1日あたり1500mg以下 |
| ステージ5 | 1日あたり1500mg以下 |
まずは手軽に「減塩調味料」から
減塩が大切だとわかっていても、実際の塩分制限は難しく感じるものです。だからこそ、まずは調味料を「減塩調味料」に置き換えてみることで、これまでとほぼ変わらない食事内容で手軽に減塩生活を始めることができます。
減塩調味料の種類と特徴は?

どんな種類の減塩調味料がある?
1.減塩醤油
特殊な方法で他の成分はそのままに、醤油100gあたりの食塩量が9g以下に低減されているものをいいます。これは、こいくち醤油の食塩分の約50%以下に相当します。製法によってはやや色が薄いことが多く、一般的な醤油に比べて味に物足りなさを感じることも。「追い麹仕込み」や「天然醸造」の減塩醤油を選ぶとコクや旨みが強く、満足感が得られます。
2.減塩味噌
減塩味噌は比較対象食品*と比べ、塩分濃度を相対差15%以上に低減されているものをいいます。麹の割合を増やしたものや複数の味噌を合わせた「合わせ味噌」を選ぶと、通常と変わらない旨みや甘みを楽しむことができます。
※一般流通品または日本食品標準成分表より
3.減塩ぽん酢
昆布や鰹のだしをしっかり効かせた商品が多く、塩辛さがなくすっきりしています。柑橘果汁(ゆず、すだち、かぼす等)を多く含むものを選ぶと、酸味により物足りなさを感じにくくなるためおすすめです。
4.減塩白だし
一般的な白だしに比べ、クセがなくあっさりしています。昆布、鰹節、椎茸などの天然素材からしっかりと出汁をとった減塩白だしを選ぶと、減塩でも十分な旨味を楽しめます。
「減塩」「低塩」どちらを選ぶのが正解?

気軽に減塩をしたい方はまずは「低塩」や「塩分控えめ」のものを、高血圧や腎臓病のために塩分制限をする場合は「減塩」と表記がある減塩調味料を選びましょう。また、「うす塩味」や「塩味控えめ」など「味」とついているものは、塩分が低いわけではないため、注意が必要です。
低い旨の表示の基準値
「低塩」「うす塩」「塩分控えめ」 など | 食品100gあたり食塩相当量0.3g以下(ナトリウム120mg以下) |
低減された旨の表示の基準値
「食塩〇%カット」「〇%減塩」など | 比較対象食品*に比べてナトリウムが食品100gあたり120mg以上減少していることかつ、比較対象食品との相対差が25%以上
・醤油:比較対象食品*と比べて食品100gあたり120mg以上減少している、かつ低減割合が20%以上
・味噌:比較対象食品*と比べて食品100gあたり120mg以上減少している、かつ低減割合が15%以上 |
含まない旨の表示の基準値
「無塩」など | ナトリウムが食品100gあたり5mgに満たないこと |
※一般流通品または日本食品標準成分表より
※出典:消費者庁「栄養成分表示及び栄養強調表示とは」、日本高血圧学会サイト
カリウム制限が必要な場合は
腎臓病や透析治療中などでカリウム制限が必要な場合、減塩調味料の選択に特に注意が必要です。多くの減塩調味料は、塩分(塩化ナトリウム)の代わりに「塩化カリウム」を使用して塩味を補っているため、カリウム含有量が通常の調味料より高くなることがあります。そのため、成分表のカリウム含有量を必ず確認しましょう。また、「塩分〇%カット」に加えて「カリウム・リン〇%カット」の表記があるかどうかを確認することも大切です。
市販調味料との比較とおすすめ減塩調味料4選
「おいしい」と「減塩」のどちらも叶えるおすすめ調味料
それでは実際にどのような減塩調味料を選んだらよいか、おすすめの減塩調味料4選をご紹介します。
1.減塩しょうゆ 姫物語

濃厚な甘みとコクの「殿さましょうゆ」を手掛ける松美屋醤油の「減塩しょうゆ 姫物語」。塩分50%カットながら、まろやかで濃厚な旨みを楽しめます。
| 商品名 | 食塩相当量(100mlあたり) |
| 濃口醤油* | 14.5g |
| 「減塩しょうゆ 姫物語」 | 7.9g |
※出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
2.旨味際立つ減塩味噌

シンプルな原材料で仕上げた、芋川麹店の「旨味際立つ減塩味噌」。老舗の味噌蔵から発見された乳酸菌を使用し、「旨み」がしっかりと感じられます。
| 商品名 | 食塩相当量(100gあたり) |
| 米みそ* | 12.4g |
| 「旨味際立つ減塩味噌」 | 7.4g |
※出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
3.三河白だし

日東醸造の「三河白だし」は、枕崎産一本釣り本かつお、北海道真昆布、国産しいたけのだしを自社工場の釜で丁寧に煮出し、白醤油と三河みりんを合わせてつくられています。あっさりながらしっかりと旨みが立ち、大満足のおいしさです。
| 商品名 | 食塩相当量(100mlあたり) |
| 某大手調味料メーカーの白だし | 13.1g |
| 「三河白だし」 | 9g |
4.減塩かぼすぽん酢

富士甚醤油の「減塩かぼすぽん酢」は地元・大分特産のかぼす果汁をふんだんに使用し、すっきりと香るかぼすの「酸味」と「だし感」で、減塩を感じさせません。
| 商品名 | 食塩相当量(100mlあたり) |
| ぽん酢しょうゆ* | 7.8g |
| 「減塩かぼすぽん酢」 | 5g |
※出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
減塩調味料選びに迷ったときは
減塩調味料について信頼できる情報を見極めるポイントは3つあります。まず1つ目は、管理栄養士や医師などの専門家による監修があること。次に「おいしさ」と「減塩」の両面から評価していること。そして最後に、塩分含有量やカリウム含有量などの具体的な「数値」まで明記されていることです。
ウェルネスダイニングでは管理栄養士監修のもと減塩調味料を厳選し、おいしさと塩分制限の両方を叶える減塩調味料セットを提供しています。塩分やカリウムの管理が必要な方も安心して使える信頼性の高さに加え、日々の料理に手軽に取り入れられることが魅力です。
減塩調味料の効果的な使い方と工夫は?

減塩調味料を効果的に使うための3つのポイント
減塩調味料を最大限に活用し、健康効果を得るためには以下の3つのポイントに注意しましょう。
1.正確に計量する
減塩調味料は、「減塩だから」と安心して無意識に使用量が増えてしまいがち。塩分制限を守るために計量スプーンや計量カップを使用し、使いすぎないように気をつけましょう。
2.料理の仕上げに調味料を使用する
調味料を最初に入れてしまうと煮詰まって味が濃くなってしまい、余計な塩分摂取につながるため、最後に入れて調味料本来の風味を活かすことで少量でもしっかりとした味わいになります。
3.保存方法と賞味期限に注意する
減塩調味料は防腐効果が通常の調味料より低く、賞味期限が短めに設定されている場合が多いです。開封後は冷蔵保存し、できるだけ早く使い切るようにしましょう。鮮度を保つ密閉ボトルタイプを選ぶのもおすすめです。
減塩でもおいしく食べるための5つの工夫
塩分を控えながらも満足感のある味わいを楽しむための工夫をご紹介します。これらのテクニックを組み合わせることで、減塩生活をより豊かに続けることができます。

1.だしの旨みを活用する
カツオや昆布、干ししいたけなどから取る本格的なだしは、減塩の強い見方です。切干大根の戻し汁やベジブロス(野菜の煮出し汁)を活用すれば、塩分制限中でも物足りなさを感じさせません。市販のだしの素よりも手作りだしの方が、塩分量をコントロールしやすいのも利点です。
2.酸味で味にメリハリをつける
味が決まらない時は、塩ではなく酢やレモン果汁など酸味を加えてみてください。ほんの数滴で素材の味が引き立ち、味に奥行きが生まれます。
3.香辛料や薬味で風味を豊かにする
七味唐辛子や山椒、カレー粉などの香辛料や、生姜やネギなどの薬味を使用すると、香りや辛みのアクセントによって味に強弱が生まれ、飽きずに楽しめます。
4.醤油や味噌の香ばしさをプラスする
醤油や味噌を加える際、フライパンや鍋の端で少し「焦がす」ように加熱すると、香りが立ちコクをプラスできます。ただし、焦がしすぎると苦味が出るので注意しましょう。
5.野菜の自然な甘みと旨みを引き出す
汁物にはさつまいもやかぼちゃなどの甘み、肉じゃがやスープにはじっくり炒めた玉ねぎの旨みを活用します。白菜やキャベツも弱火でゆっくりと加熱すると甘みが増します。野菜本来の味を活かす調理法を活用し、塩分控えめでも満足度の高い料理に仕上がります。
家族みんなで楽しむひと工夫

家族みんなで減塩を楽しむ工夫として、減塩調味料の「味比べ」をしてみてはいかがでしょうか。数種類の減塩調味料を少量ずつ注ぎ、家族みんなで「これが好き」「これは苦手」と意見を出し合ってみるのは楽しいものです。
減塩に無関心だった家族が減塩調味料に目が留まるようになり、よりお互いの理解が深まります。
管理栄養士おすすめの減塩生活の始め方

初めての減塩生活 ー実践3ステップー
ステップ1 まずは1週間「写真で食事日記」
まずは継続的に、「食事日記」をつけることから始めましょう。スマートフォンのカメラで写真を撮るだけで、毎日の食事を手軽に振り返ることができます。どんな味付けの食事を食べたか、最もよく食卓に並ぶ味付けと調味料は何だったか、把握することが大切です。
食事の傾向を可視化できれば、最もよく使用する調味料を減塩調味料に置き換えてみる、同じ味付けを変えてみるなど、自分の好みに合う減塩方法を見つける手助けとなります。
ステップ2 調味料の幅を広げよう
減塩調味料は醤油や味噌だけではありません。白だしやぽん酢など様々な減塩調味料があります。様々な減塩調味料を日替わりで活用し、計画的に味の変化をつけましょう。そうすることで、楽しみながら味覚が鋭くなり、食事の満足度を高められます。
ステップ3 食材の自然な旨みを活用する「楽しむ減塩」へ
減塩生活に慣れてきたら、調味料に頼らず食材本来の旨みを引き出す食事へと意識を変えていきましょう。昆布やかつお節、トマトやきのこの旨み、じっくり炒めた玉ねぎやキャベツの甘みなど、少しづつ取り入れていきましょう。
これにより、「調味料で味をつける」から「食材の味わいを楽しむ」に意識が変わり、減塩を無理なく長期的に継続できるようになります。
よくある質問(FAQ)

Q1 :減塩調味料を使うと味が薄くなりませんか?
最近の減塩調味料は製法の進化により、以前より格段においしくなっています。特に、旨み成分を凝縮した製品を選ぶと、塩分は控えめでも十分な味わいを楽しめます。
Q2:減塩調味料は通常と同じように料理に使えますか?
基本的に通常と同じように使用できます。より楽しむコツとして、加熱の際は塩味が飛びやすいため、仕上げに加えると効果的です。また、減塩醤油はやや色が薄いことが多いため、見た目の色で判断せず、使用量をきちんと計ることが大切です。
Q3:カリウム制限中に使える調味料はありますか?
カリウム制限中の方は、カリウムを最大限抑えた減塩調味料を選ぶことが重要です。ウェルネスダイニングの「カリウム&塩分制限調味料セット」は、市販品に比べてカリウムを56%カットしており、腎臓病や透析治療中の方でも安心してお使いいただけます。
Q4:減塩調味料は家族で使えますか?
健康であれば家族全員で使うことができます。むしろ、日本人の多くは塩分を摂りすぎている傾向にあるため、減塩調味料を取り入れることは家族の健康維持にもつながるでしょう。味わいにこだわった減塩調味料を選べば、家族みんなで美味しく減塩できます。また、子どもの頃から薄味に慣れることで、将来の生活習慣病予防にもつながります。
減塩調味料でおいしさと健康を両立するために

本記事では、「どんな減塩調味料を買ったらいいかわからない」「カリウム制限も必要だけど味も大切にしたい」と減塩調味料やカリウム制限調味料でお困りの方に向けて、減塩調味料の選び方や種類、効果的な使い方、おすすめ商品まで徹底解説しました。
塩分やカリウムの制限が必要な方にとって、毎日の食事は治療の一環でもあります。しかし、それは味の満足感を諦めることとはイコールではありません。適切な減塩調味料を活用すれば、「おいしさ」と「健康」の両立は十分可能です。
「何から始めようかな」と迷ったら、ウェルネスダイニングの減塩調味料セットから始めてみてはいかがでしょうか。減塩調味料をスーパーで探す手間や時間を、大切な家族と過ごす時間に変えて、もっと手軽に、おいしい減塩生活を楽しんでくださいね。